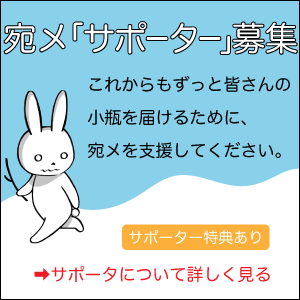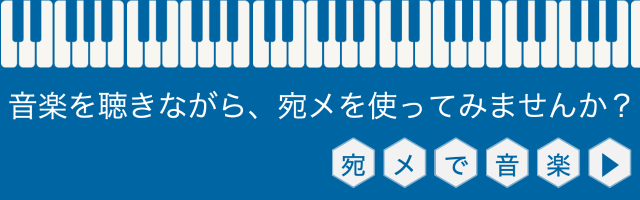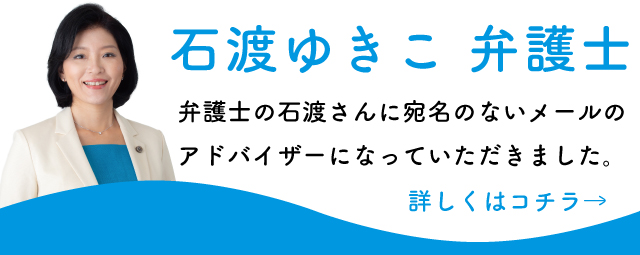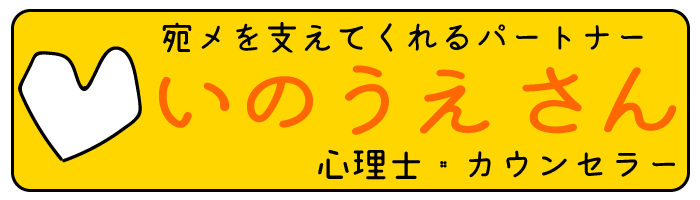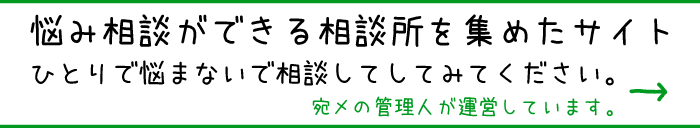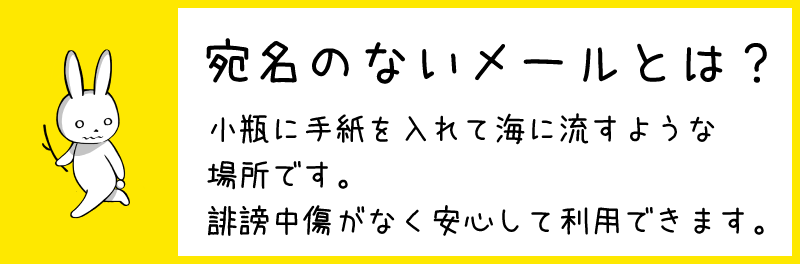
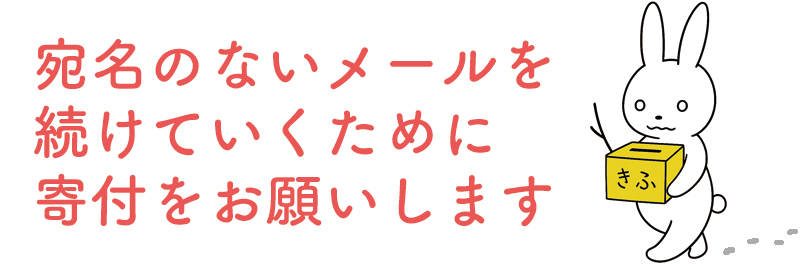
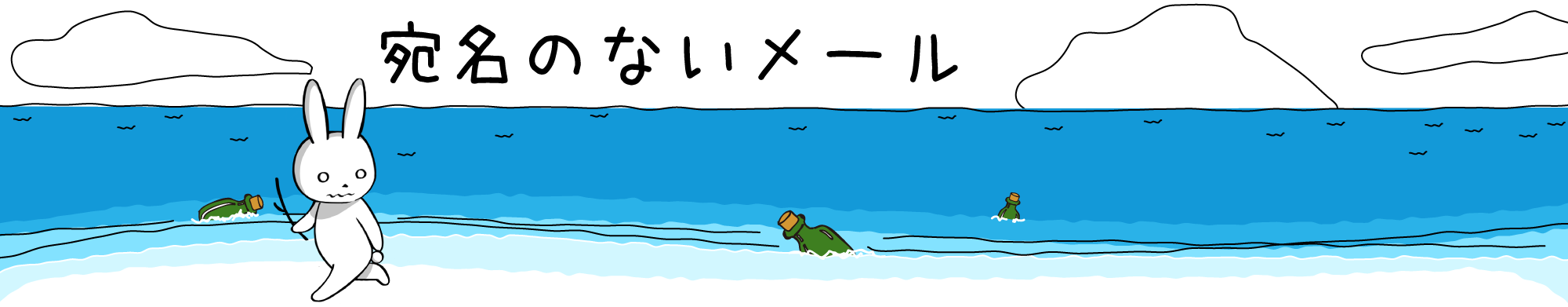
ニュースで量子コンピュータを見聞きしたり、ネットを見たり、量子コンピュータってどうしてもひとまとめ、ひとくくりで聞こえてしまわないか?そうやって話を聞くと、混乱しやすくなり理解できなくて、私はとても困った。
混乱し難く、理解しやすくなるためにも、量子コンピュータに種類が色々あると知っておこう。
▫️量子コンピュータの種類
何種類もある。なぜいくつもあるのか、
① 量子ビットの実現方法が多様だから
② 解きたい問題の性質が異なるから
③ 技術的・経済的な制約が異なるから
④ 量子力学の多様性そのものが反映されているから
◻︎ゲート型
• 使いたい量子の特徴:• 重ね合わせ(superposition)
• 干渉(interference)
• もつれ(entanglement)
• 目的:• 任意の量子アルゴリズムを構築し、汎用的な計算を可能にする。
• ショアのアルゴリズムやグローバー探索など、量子の論理的な構造を最大限に活かす。
日本においても、理化学研究所・富士通・NTTの連携により、2023年に国産初のゲート型量子コンピュータ(64量子ビット)が公開された。2025年には256量子ビット規模の実機も登場し、誤り訂正技術(STARアーキテクチャ)を組み込んだ開発が進行中である。これらの国産機は、超伝導方式を採用し、クラウド経由での利用も可能となっているが、現時点では主に研究用途に限定されており、商用展開や教育普及はまだ始まりの段階にある。
日本のゲート型量子コンピュータは、量子ビットの制御精度や誤り訂正技術において世界的にも高い評価を受けているが、社会的認知や人材育成、実用化に向けたエコシステムの整備は今後の課題である。量子技術の社会実装を進めるためには、技術開発と並行して、教育・編集・アウトリーチなど多様な役割による橋渡しが不可欠である。
IBM Quantum System One(日本)の方は、
量子ビット数:27量子ビット
IBM Cloud経由で世界中の実機にアクセス可能
言語やフレームワークは
Qiskit, Q#, Cirq, Braket
ゲート式量子コンピュータは、量子ビットに量子ゲートを順番に適用して状態を操作するモデル。
その操作の流れを視覚的に表したものが、量子回路図(Quantum Circuit Diagram)。
◻︎アニーリング型
• 使いたい量子の特徴:量子トンネル効果(quantum tunneling)
• 量子揺らぎ(quantum fluctuation)
• 目的:複雑な最適化問題を、エネルギーの谷を滑るように解く。
• イジング模型に問題を埋め込み、最小エネルギー状態=最適解を探す。
アニーリング型量子コンピュータでは、計算の途中で量子状態を保持する必要がないため、ゲート型ほど厳密な誤り訂正は必要とされていない。ハードウェアの構成が比較的シンプルで、制御も安定しやすく、すでに特定の最適化問題に対しては実用化が進んでいる。実際に、D-Wave社のアニーリング型量子コンピュータは、製造業、物流、金融などの分野で導入されており、企業や自治体が現場の課題解決に活用する事例も増えている。
言語やフレームワークは
Ocean SDK, Leap, Digital Annealer API
◻︎イオントラップ型(ゲート型の一種)
• 使いたい量子の特徴:長時間コヒーレンス(coherence)
• 高精度な状態制御
• レーザーによる量子操作
• 目的:高精度な量子ゲートを実現し、誤りの少ない計算を可能にする。
• ゲート型の一種として、物理的な安定性と美しさを追求。物理的な実装が「イオン」なだけで、計算モデルはゲート型と同じ。
IonQ(米国)は、2025年現在、世界で商用化が進んだイオントラップ型量子コンピュータ企業のひとつ。単なる研究機関ではなく、実際にクラウド上で量子計算を提供し、産業応用を進めているという点で、非常にユニークな立ち位置にいる。
Quantinuum(米・英)
• 応用展開:量子暗号(Quantum Origin)や量子化学(InQuanto)など、ソフトウェア含む垂直統合で商用展開中。
• 資金調達・提携:NVIDIA、JPMorgan、三井物産などと連携
Qubitcore株式会社は、日本でのイオントラップ型量子コンピュータの実現に挑む。
現在、誤り耐性型量子コンピュータの開発を進めており、2030年の商用稼働開始を目標に、挑戦を続けている。
◻︎他もスピン型、トポロジカル型など。
スピン型は電子のスピンを使い、トポロジカル型はエラー耐性に優れた理論的方式。
◻︎ 疑似アニーリング技術
富士通やNECが疑似アニーリング技術を用いた量子的最適化サービスを展開しており、古典コンピュータとのハイブリッド構成によって社会実装が進行中である。疑似アニーリング技術とは、現在主流の古典コンピュータ(最小単位が1ビット〈0・1〉)上で、量子アニーリングの数理構造を模倣する手法である。これは量子状態の厳密な物理的再現ではなく、量子的な振る舞い(例えばイジングモデルに基づくエネルギー最小化)を古典的なアルゴリズムで模擬的に実行するものである。実際の量子干渉や重ね合わせは起きていないが、構文の設計、アルゴリズムの理解、思考訓練には十分に役立ち、現実の業務課題に対しても高速な最適化が可能となっている。
2025/9吉日

お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください