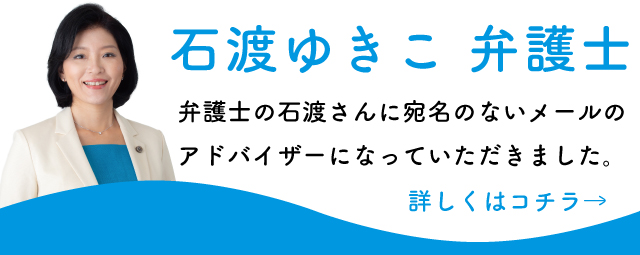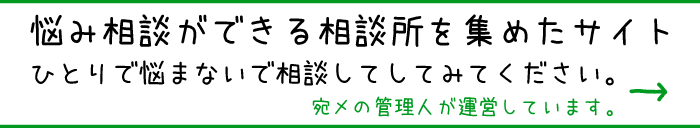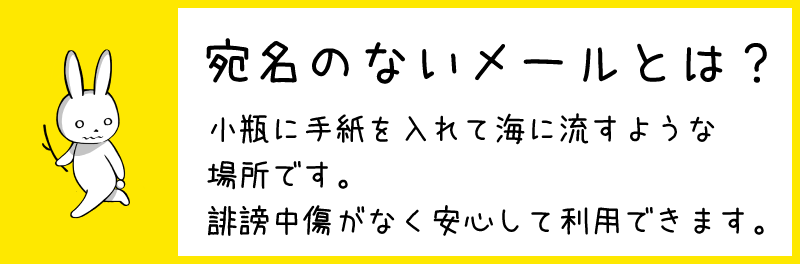
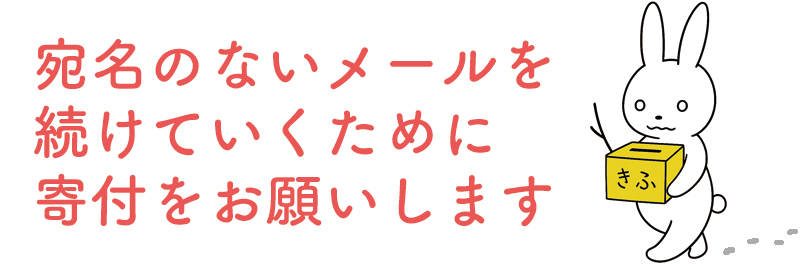

虐待の話を聞くとき、暴力を振るう親を、誰もが非難する。
私はそうじゃない。子どもが暴力を振るわれ、自分も殴られているのに、そのまま離婚もしない、離婚しない理由を子どものせいにする母親に、激しい怒り、憎しみを今も抱く。
虐待で「あんたなんか産むんじゃなかった」という言葉が子供を傷つける。
私は私たちがいることで、母が暴力を耐えなければならない、貧乏を耐えなければならないと思わされた。
だから一時期は、私たちは生まれてくるんじゃなかった、と、幼稚な考えだった。
成長し、この人何を言ってるんだ、離婚しないのは自分の都合じゃないかと気づいた。私らが成人し、家を出て、うざい親から離れると、必死で連絡を取ってきた。
子どもが親を見捨てられないものだと、思い込んでいたが、私は捨てるつもりだった。
母は、女性が自由に仕事をして、夫に頼らず生きるという姿を直視できなかった。私たちが得る収入の額を知って、自分の生活、父の収入との比較をし、私たちを、うらやむ面はあった。
私は収入額なんて言っていない。母に圧力かけられて育った姉が言ったのだとわかる。長女の姉は、父の暴力と、母の無言の虐待、将来の期待で、壊れていった。
私が同じ仕事に就いたために、私との比較され、精神におかしさが見られる、まともな仕事ができないと左遷され、それが何を意味するかを親に知られた。
それから後の母の振る舞い。父はあきらめていたし、もとより子どもに将来の自分を期待していない。自分で働くことや、家事の切り盛りもできない母が、どーんと私に襲いかかった。
ある日、叔母を連れて私の住むところにやってきた。なんの連絡もなく。
そうして叔母から、母親を大事にするよう、将来のことを考えるよう、唐突に言われた。そう母が叔母に頼んでいたからだろう。
自分で言えないのは、私が母を疎んでいることを感じていたからだ。
口では立派な母のように言っていても、実態はクソ母だった。
私が着飾るのを苦手なのは、鏡を見ているだけで、髪を整えているだけで、子供のくせに、余計なものに興味を持つな、そう言った。
ほとんど無関心のくせに、悪口だけは言い続けた。子供らが目に入るから、子供のこと、父の収入や性格のこと、知り合った人のこと、叔母らのこと、誰一人褒めない、貶すだけ。
私が母のそれらを言えなくなったのは、亡くなったから。
当時はショックを受ける自分が、よくわからなかった。
亡くなった親の悪口を言うことに抵抗があった。
だけど、傷つけられたそれらは、亡くなったことで消えてはいない。

この小瓶にはお返事ができません