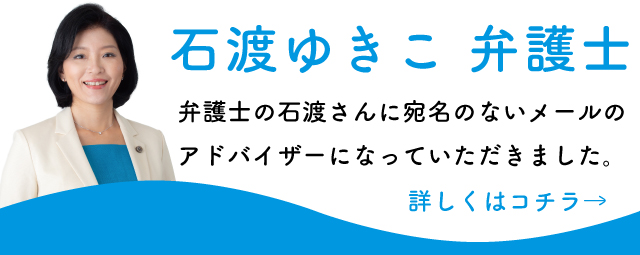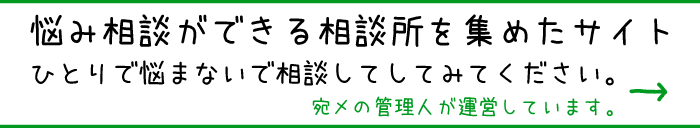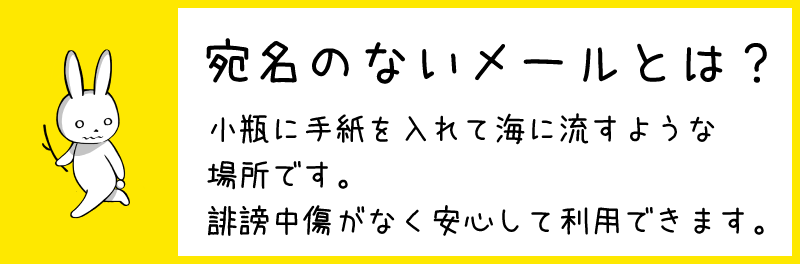
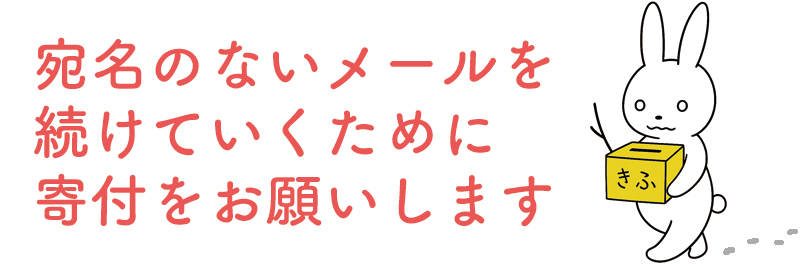

学年中に俺の悪口が渦巻きだすのに、あまり時間はかからなかった。
父さんと母さんは全てを鵜呑みにして、どっちの育て方が悪いと毎日大喧嘩、結果家族は離散した。
学校にいけなくなった俺のもとに、毎日彼奴が訪ねに来た。
心配し過ぎだと思ったが、正直嬉しかった。
その後瑠夏がどうなったのか、俺は知らないまま卒業した。
児童相談所で働き出すようになってから、いじめる子にも事情があることを知った。
無関心な親の気を引きたかった少年、親からのストレスをどこにぶつけていいか分からなくなってしまった少女。
(もしかしたら、瑠夏にも何かあったのかも知れない。)
いつしか俺はそう思うようになっていた。
もしまた会えたら友達に戻れるかもと、そんな淡い期待を抱いていた。
そんなものはすぐに壊されてしまうと知らずに。
「失礼するね。今日の体調はどうだい。」
一時保護中の子の部屋の見回りから一日は始まる。
最後の部屋は、昨日からいじめ加害によって保護された男の子だった。
「おはよう。よく眠れたかい。」
そう問うと、彼はつまらなさそうに、生意気に答えた。
「子供扱いしないでもらっていい。」
いじめをした子が素の自分を見せるのには、長くかかるとよく分かっていた。
そういう子には多くの刺激を与えず、尚且つ寄り添ってあげることが大事だと学んできた。
「そっかそっか、ごめんね。さて、この後時間空いてるし、君と話をしたいな。」
すると彼は興味を示したようで、話したいと頷いた。
子供らしい一面にひとまず安心していると、彼はいきなり俺の頬を打った。
「いっ……。な、何するんだい。」
「僕さあ、楽しいんだよね。こうやって、人のこと虐めるの。」
そう言って馬乗りになる少年の顔は全く楽しそうではなく、むしろ苦しさが滲み出ていた。
「やめろ。それは君のためにも俺のためにもならない。」
どうにかして打つ手を止めさせようと、彼の両手首をぐっと捕まえました。
と、彼はあーあーと暴れ出しました。
「僕、僕は、僕はさあ!楽し、楽しいから、だから虐めて、るの!」
嘘じゃないんだと泣き喚く彼を、五人ほどの大人が囲んだ。
少年がこうなったのには、誰か原因がいる気がしてならなかった。
その首謀者を想像しようとすると、頭にふっと浮かび上がってくる記憶があった。
『私だけは味方よ。』
その日は、彼奴とともに暮らす家に帰れなかった。
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください
 nanaha.
nanaha.
彩紗さんへ
お返事ありがとうございます!
確かに実際にはいないかもしれないですね😓
本当に過酷な学生時代を過ごした分、友達に救われていてほしい、という願望を文字にしてみました!
僕も彼らがめちゃめちゃ羨ましいです(´・ω・`)
僕もその考え方と近いですね。
いじめっ子に背景があるっていうのも事実ですが、だからといっていじめていい理由にはならないはずです。
一二三が仄仄と仲直りしたいと思っているところを参考にさせていただきました☺️
一二三が本当に自己犠牲の人で、見ているこっちがしんどくなるくらいなんです…。
そんな一二三に独歩がいるということが、唯一の救いなんですよね。
その関係性が好きで、小説に出してみました!
この子は本当に僕の創作ですね。
全く情報を調べずに書いたし、少し書いたときから時間が経ったもので覚えてないんです💦
覚えているのは「意図のないホラー」をテーマにしたこととかですかね。
仄仄は本当に理解できない悪役なんです!!!!
ぜひYouTubeに上がっているドラマトラック聞いてみてほしいです🎧️
『錆びつけば進めず、臆すれば誇りを失う。故に我々は己に否を焼べ、火を灯し続ける』
『The Block Party -後半-』
『Not For You』
この三つを聞けば、三人の関係がわかると思います!
本当に!聞いてみて!ほしいです!!!
p.s.
M-1、たくろうが優勝しましたね!
カベポスターが敗者復活あがらなかったのは残念でしたね💦
真空が最終決戦落ちたのはすごいびっくりしました!
僕はヤーレンズ好きなので、最終決戦落ちたのは本当にがっかりしました😭
彩紗さんの感想もぜひお聞かせください!
 彩紗☾··
彩紗☾··
「彼」と「親友」の友情、いいなぁ。
学校に行けなくなった時に"毎日きてくれる友達"がいる人って、実在しないよね、、
と思う私はひねくれてるね(´•̥ ω •̥` )
2人の絆が羨ましくて僻んでしまった
「いじめる子にも事情がある」
私は、いじめる方が一方的に悪いっていう考え方なんだけど、間違ってるかな
どんな事情があっても、いじめていい理由にはならないと思う。
「親友」、あんなことされたのに瑠夏と仲直りしようと思ってたんだ
心が綺麗で広い人なんだね
児童相談所って、どこもこういう子いるのかな
反抗的な子はいると思うけど、児相で働いてる人に暴力はびっくりした。
「親友」の勘が当たってるなら、この子もある意味でいじめの被害者ってことだよね
瑠夏みたいないじめの首謀者が、他にもいたっていうことだね…
あんなにホラーな首謀者は、滅多にいない気がするなぁ。
「親友」の過去(生前)、壮絶だった
悪役が好きなのはわかるよ?
私も好きな悪役がいるから。
だけど
「読んでいる誰にも共感されないような」ってどんなのだろ?
( ˘•ω•˘ ) ナヤムナー
どの悪役も、誰かしらに共感されてる気がする
おすすめしてくれたヒプノシスマイクの公式サイト見てみたよ
YouTubeもいくつか見た。
邪答院仄仄が瑠夏で、伊弉冉一二三が「親友」だよね?
で、観音坂独歩が「彼」
誰にも共感されないような根っからの……
うーん…仄仄?
なっぱの小説で、初めて出てきた理解できないキャラなんだよね、瑠夏
だからこそ、スピンオフで瑠夏のバックボーンを読みたいな、とは思った!
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください