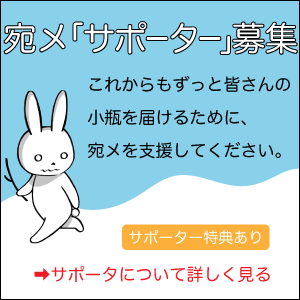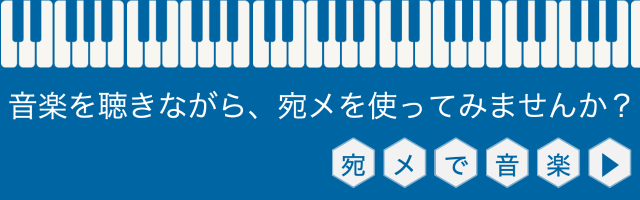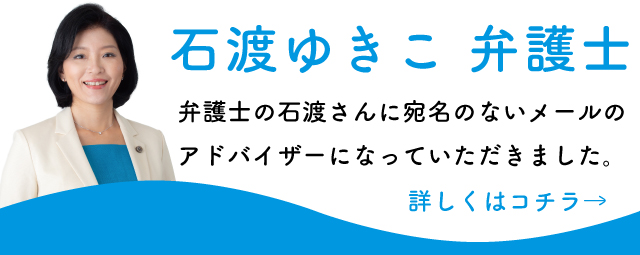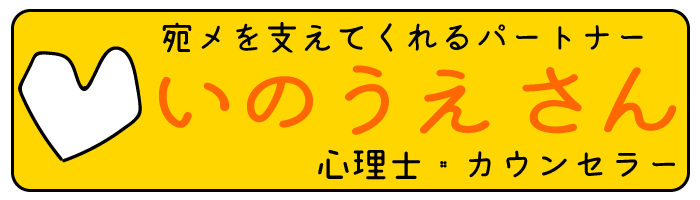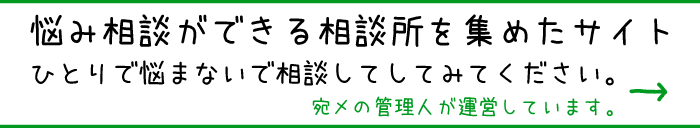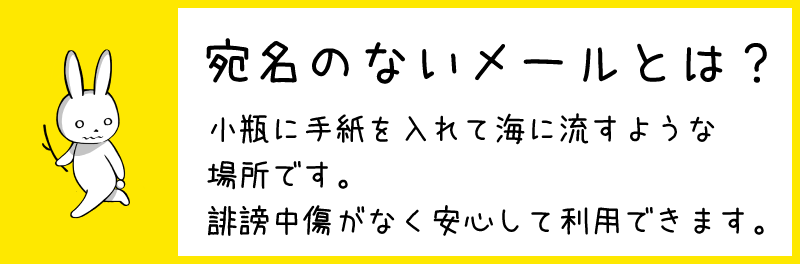
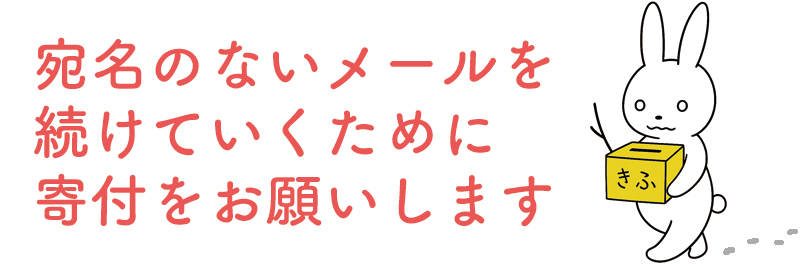
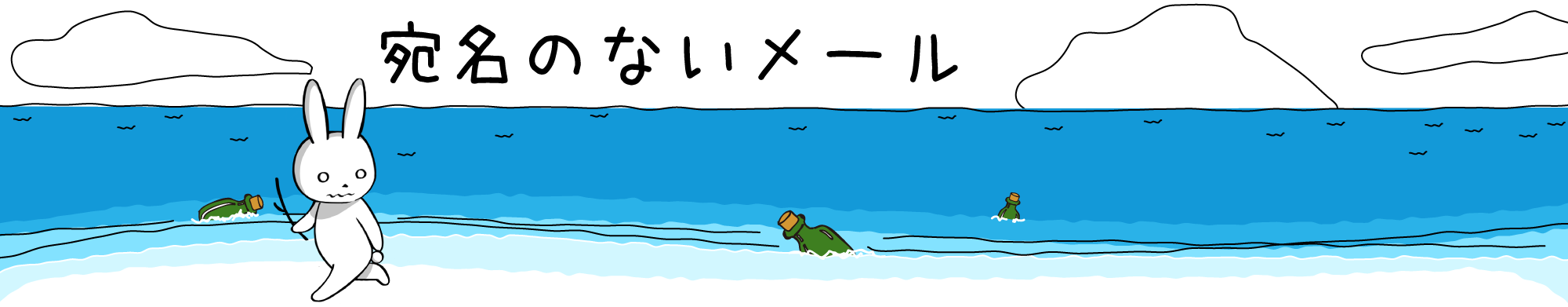
最近たまたまテレビで、ヤングケアラ ーの特集をしていました。「ヤングケアラー」この言葉を私は聞いた ことがなかったので、なんだろう?と思って見ていました。
ヤングケアラ ーとは、家族の世話や精神的支えを担う若者のことで、中学生の17人に1人、高校生の24 人に1人いることが、国が行った初めての実態調査でわかったそうです。そのうち1割以上が家事や介護の 時間が1日7時間を超える子どももいることを知って、私はとても驚きました。
日本では、ヤングケアラーが長い間見過 ごされてきた現実があるそうです。家族が家族のケアをするのが 当 た り 前 と い う 考 え が あ った り 、 本 人 が 自 覚 し て い な か った り し て 、 周 り の 人 も 「お 手 伝 い を す る い い 子 だね。」ということで終わってきました。コロナで 介護サ ービスが使えなくなって、もっと負担がかっかて いるのもあると思います。でも、ほとんどのヤングケアラーは誰にも相談した経験がないそうです。家族が 困っていたら手伝うのが当たり前だと思っていたり、かわいそうだと思われたくない、相談してもきっとわ かってくれない 、相談しても仕方ないという理由のようです。だから子どもたちはさらにしんどくなってい くと思います。1日に何時間も家事や介護をしていたら 、勉強や寝るための時間が不足してしまいます。す ると学校生活に支障をきたしてしまうかもしれません。子どもは子どもらしく友だちと遊んだり、ゲームを したいはずです。それでもヤングケアラ ーの子どもたちは、自分の時間をさいて家族のケアをしています。
私だったら学校もいっぱい行きたいし、しっかり寝たり、友だちと遊んでゲ ームもしたいです。子どもだっ た ら 誰 で も そ うだ と 思 い ま す 。
テレビの特集では、障がいのある19才の弟の世話をする21才のお姉ちゃんについて取材をしていました。 そのお姉ちゃんは、就職を考えたときに弟の世話をするために自宅から遠い所では働けない、何か弟にあったらかけつけられる所や休みやすい所がいいと、自分がやりたいことより弟のそばにいることを 一番に考え ていました。
私には将来、学校の先生になりたいという夢があります。ヤングケアラ ーと呼ばれる子どもたちにもきっと 夢があると思います。自分の夢をあきらめなくていい方法を見つけてほしいです。そして、周りの人も 「ヤングケアラー」という存在を知っておく ことや、無関心にな らず気にかけて、相談しやすい環境をつくるこ とが大切だと思います。
私がこの特集を見て感じた ことは、人間にとって 一番大切な ことは「想像力」かもしれないという ことです。 相手の気持ちを想像する、相手の立場だったら、自分はどうだろうと想像力をはたらかせることで、思いや りのある社会になると思います。ヤングケアラ ーの子どもたちも夢をあきらめなくていい、そして自分の人 生を楽しめるような、そんな社会になってほしいです。
だから、私は夢をあきらめない。
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください

ななしさん
鶴さんの夢、世界中の人達の夢。全部叶ってほしいです
ヤングケアラーの子たちが少しでも自分らしく居れるように、行政の支援がもっと拡大してくれたらな
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください