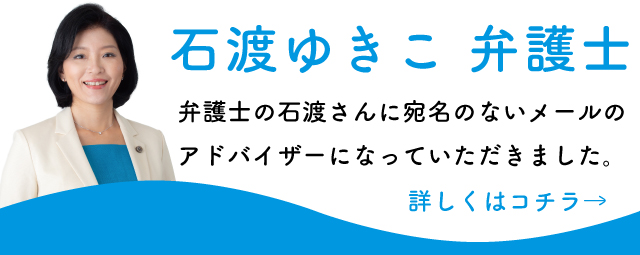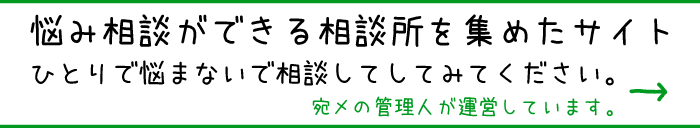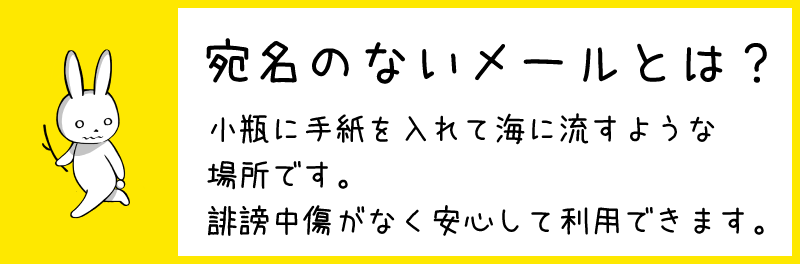
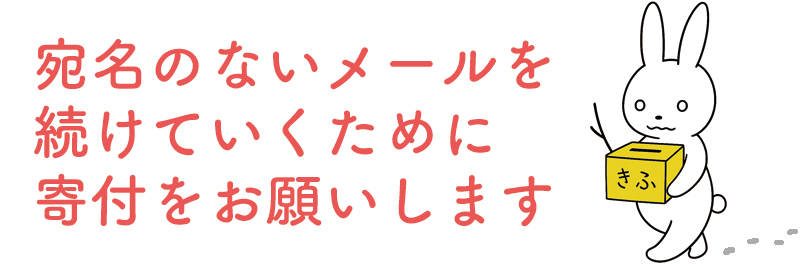

色々解決したとはいえ、やっぱり気力は完全には戻ってこなかった。
やっぱりアルビナが死んだことは、相当なショックだったらしい。
他人事みたいな言い方なのは、実際話している時はそんな風に思ったことはなかったからだ。
失ってから大切さに気付くとは、よく言った話だ。
「いいや、取り敢えず勉強しよ…。」
俺の、良い癖でも悪い癖でもあるところ。
こんなだから、ガリ勉って陰口叩かれてんだろうな。
俺が一部の人間から煙たがられていることくらい、一応気づいている。
と、そこでコンコンと扉がノックされた。
「瑠唯、ちょっと良いか?」
ちょっと待って、どういうことだ。こんな展開あってたまるか。
「ごめん、もう一回整理して良い?」
「ああ。急に言ってしまったからな。」
混乱する頭で文章を組み立ててゆく。
「つまり、俺が寝る前につけてるアイマスクがVRゴーグルで、鏡の世界は仮想空間だったってこと?」
「そういうことだ。」
「え、じゃあアルビ…そこで会った人っていうのは。」
「全部架空の人物だ。」
つまり、アルビナなんて人物は居なかったってことになる。
そんなの、そんなの…。
「何で、そんなことしたの?」
「…私達が、瑠唯の将来を狭めてしまったと危惧した結果なんだ。」
そこから、父さんは語りだした。
「私や母さんは、ちょうど就職氷河期の時代だったんだ。だが、人より勉強ができた私達は、ちゃんとした職につけた。だから、自分の子供にも勉強ができるようになってほしかったんだ。」
就職氷河期。バブル経済が崩壊した直後、経費削減のために大量のリストラなどが行われた時代だったと歴史で習った。
「でもな、きっとやりすぎたんだ。」
そういった父さんの顔には、深い後悔が刻まれていた。
「昔、お前と少し揉めた時、『僕は勉強ができなきゃ価値がない』って言ってたんだ。私はそれがショックで、このままじゃいかんと思ったんだ。」
少しも覚えていないけど、きっと当時の本心なのだ。
なぜ言い切れるかといえば、今もその思いは変わっていないからだ。
「知り合いが、仮想現実によるコミュニティをつくるプロジェクトを進めていてな。旧知のよしみで、実験体となる代わりに貸してもらったんだ。」
「そこで、何で僕に使わせたの?そこだけわからないんだよ。」
すると、父さんは優しい顔をした。
「瑠唯、アフガニスタン行ったことあったよな。瑠唯が興味を持ったことを応援してやりたくて。」
父さんは俺の頭に手を伸ばし、優しく撫でた。
「瑠唯が、仮想現実の誰かの価値観によって変われたというなら、私達は本当に嬉しいんだ。」
「…俺、変われた?」
「ああ、自分が変われたと思うなら、きっとな。」
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください
 nanaha.
nanaha.
彩紗さんへ
お返事ありがとうございます!
描いてて楽しくなっちゃって入れた要素なんですけど、分かりづらくなかったですかね💦
瑠唯は非現実的なものを嫌いそうだし、納得しそうな要素を入れてみました。
どうなんでしょうね?
アルビナは存在している方が良かったのか、しないほうが良かったのか…。
でも、実際戦争に苦しむ方はいますし、アルビナを通してそれに気づけたことは良かったかと(*´ω`*)
わかります!
僕も書いてて、瑠唯かっこよくなったなと思います♪
このまま、かっこよくなり続けてほしいですね✨️
はい、元気が一番です!
暑い日々が続きますが、健康第一で🎐
 彩紗☾··
彩紗☾··
え、仮想空間……?
アルビナは実在しなかった…
衝撃の事実だ
まさかの展開だったなぁ
私は、Peaceの中で鏡の世界が実在してると思ってたからびっくりした
だけど思い返してみて「そういうことだったのか」ってすごく納得した
ディズニーみたいな喋り方、とか
翻訳機能が良くなってきた、運営頑張ってるんだ、とか
あれはそういう意味だったんだね
仮想空間だったからだって、腹落ちした
「もうちょっと生きたかった」って言ってたアルビナが架空の人物だったことは、良かった、…のかな?
そう思いながら戦争で命を落とした子、きっと実在するよね
だからやっぱり、戦争を忘れてはいけないって思った
瑠唯は、アルビナに会って変わったと思うな
クールな印象だったのが、なんか熱くなったイメージ
「アルビナとの約束を守る」って言った時の瑠唯、最初の頃とは違ってるよね
すごく格好いい
この先、瑠唯、明來、設楽先生がどうなるのかドキドキしながら待ってるね!
残暑お見舞い申し上げます
なっぱ、お元気ですか?
いろいろあるけど、お互い元気でいようね
(。・ω・。)ノ))
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください