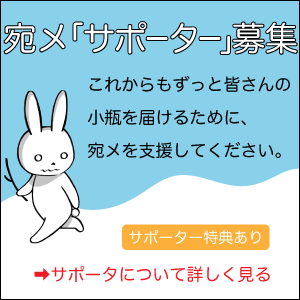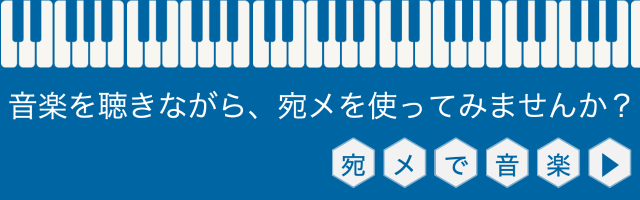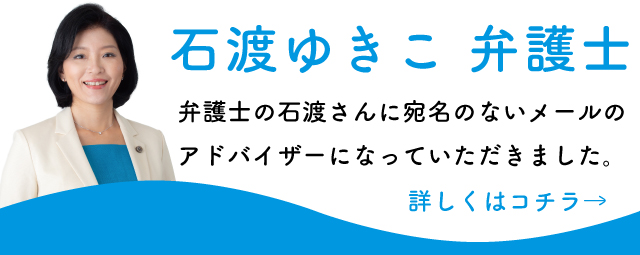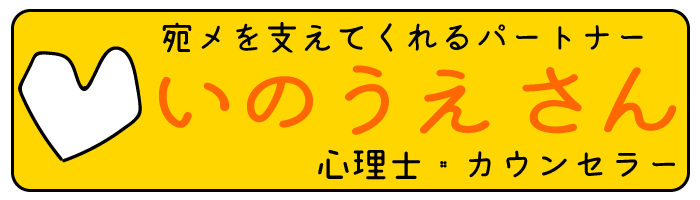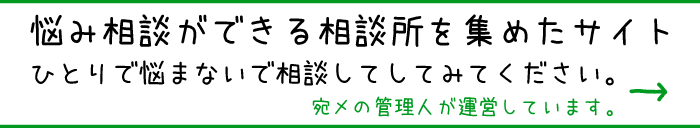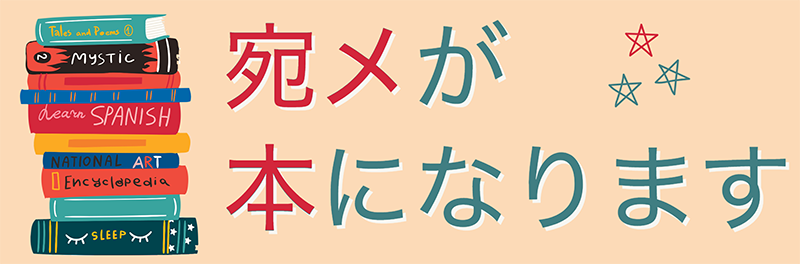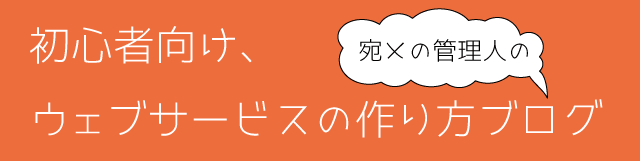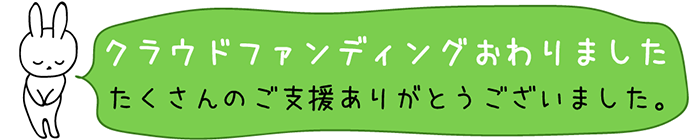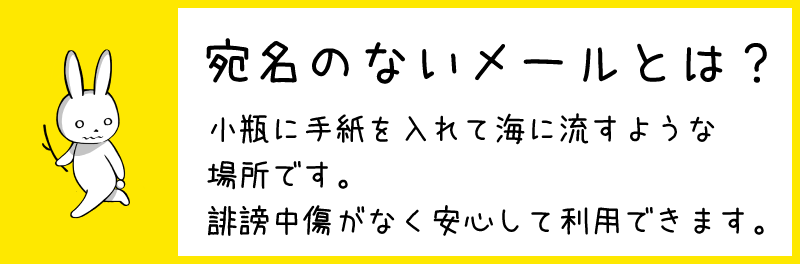
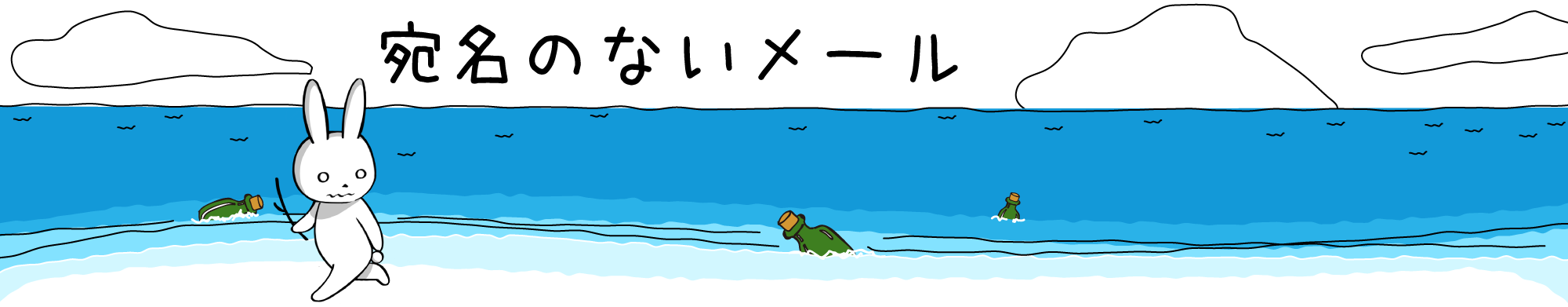
新天地に向けての小瓶。
12月に、同期に1年遅れて卒論を出した。
内容はぼかして言うと、日本古典文学における親子関係と〈病〉。
三角かっこ〈〉を使う時は、特別な意味を持たせたい場合だと学部2年生の頃に教わったなぁ…。
ここでいう〈病〉は伝染性のそれではなく、精神疾患のこと。
14のときから私を苛みつづけたそれが、まさかまるっと自分の研究になるなんて、私は考えてもみなかったぞ!
2020年はコロナ禍初年であり、私が昔からの体調を拗らせて休学した年だった。
思えば、私の10代は〈病〉とともにあり、また〈病〉という記号に両親への不安と不満を隠蔽し続けていたのであった。
それを、ひとつの文学作品の解釈にまで昇華させることができたことを、本当に感慨深く思う。
私は、卒論で書いたこの研究テーマを携えて大学院の修士課程へと進む。
博士課程にまで進めるかはわからない。
まずは、修士論文を書かなくちゃいけない。なんらかの形で研究結果が世に出せたらいいなとも思う(学内学会誌のレベルであっても)。
卒業と同時に教員免許も取れる(はずだ)し、高校の先生にだってなりたい。
これでいいのかな、このままではいけないはずだ。
もうずっとそればかり宛メでは繰り返してきたけれど、なんだかんだで高校生くらいの自分が思い描いた形の未来に現実では近付いていることに驚いてしまう。
だって、院に行きたいって、高校生くらいから言ってる!(笑)
23歳になっても、
今年の5月に宛メを使い始めてまる10年になっても(!)
私は相変わらず子どもだし、ぐずぐずやってる。
でもたしかに、かつての自分と今の自分は何かが違うのだ。
年明け前からちびちびと読んでいたR.D.レイン『自己と他者』はきっと10代の私を本当の意味で締めくくる読書だったと思う。
その中で紹介されていたウィニコットの「過渡的対象」という用語は間違いなく私がずっと言葉にしようと格闘してきた私の認知の癖を言い当てていた。
なんだ、そんな一言で言い表せるのか、という拍子抜けの一方で、これで次に進めるという安心もあった。
自分より若い中高生のユーザーの小瓶を拾いながら、かつての自分の姿を探してみる。
しかし、そこにあるのは遠く隔たってしまった私なのだ。何かが、確実に変わって、大人になってしまった。
もうあの頃と同じ温度で彼/彼女たちに同化しきれなくなってしまったことに茫然としてしまう。そして、私がそこに飲み込まれることはもうしばらくないだろう。
感じられた痛みを感じられなくなること。
これはかつての私が本当に恐れたことだった。
痛みはたしかになくなった。
だが、私はたしかに憶えているのだ。感覚は遠くに行ってしまったけれど。もうあの頃の微熱っぽさはないけれど。
私には手首の傷も残っているし、辛かったことも悩んだことも死んでやろうとしたことも、ちゃんと私の中に記憶として残っている。
本当に必要なことは、身体がおぼえているから。
忘れても、思い出せるから。
教えてもらった言葉を、大事にきちんともっている。
いつだって私は、パンドラの匣を開けられる。
だけど、その蓋を閉じたまま、大事に匣を抱えていることもできる。
この1年くらいで、生活に精神のピントがようやく合うようになってきた。
私は、無数の私を物語の中に見出しながら、4月からの研究生活という〈物語〉をきっと紡いでいけるはずだ。
と私の無意識なるものを、少しだけ、信じてみようじゃないか。
新型コロナウイルスの症状が快方に向かいつつある、明け方の病床から。
(鼻詰まりがひどい)
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項

ななしさん
あなたのお名前は、ずっと以前からお見掛けしていました。
もしかしたら、何回かお返事をしたこともあったかもしれません。
一時期、お見掛けしなくなってしまったので、どうされているのだろうと思っていましたが、過去に望んでいたような道に進まれることになったのですね。
過去の記憶と共に、先に進んでいかれるあなたに、幸あれ。
お体おいたわりください。
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項