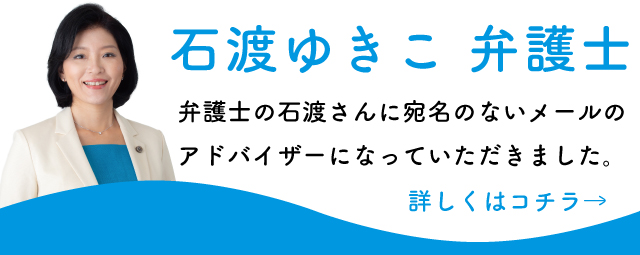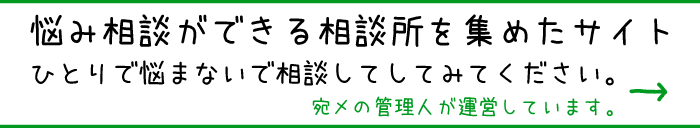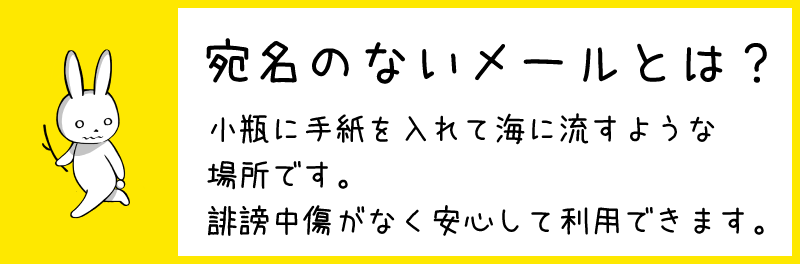
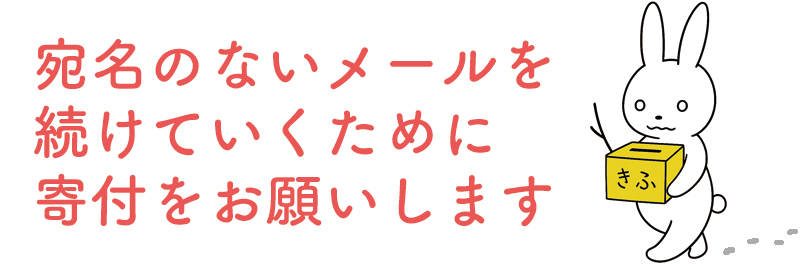

最近、教室の空気が、妙に冷たく感じる。
生徒たちの笑い声が遠く、まるで水の底で響いているみたいだった。
黒板に書いた文字は滲み、チョークの粉が手にこびりついて、洗っても落ちない。
何を教えていたのかも、もう覚えていない。
初任の春、私は希望の塊だった。
「子どもたちの未来を支える仕事」なんて、綺麗な言葉を信じていた。
でも現実は……そう叱っても、褒めても、届かない。
誰の心にも、私の声は沈んでいくばかり。
保護者からの苦情、生徒からの嘲笑、そのどれもが、心に釘のように刺さって抜けなくなった。
夜、職員室の蛍光灯がひとつだけ点いている。
誰もいないはずの職員室で、私はテストの山を前に固まっていた。
赤ペンを持つ手が震える。
最近はもう字が書けない。
「あなたには教師の資質がない」と保護者に言われた言葉が、何度も頭の中で反響する。
窓の外では風が鳴いていた。
まるで世界そのものが私の代わりに泣いてくれているように。
家に帰っても、部屋の明かりが眩しく感じる。
食べ物の味がしない。
シャワーを浴びても心の汚れだけは取れない。
飼ってる猫ちゃんと遊んでも何も感じない
鏡を見ると、そこに立っているのは「先生」じゃない。
ただの壊れかけた女だった。
ずっと眠れない夜が続く。
教科書を抱きしめて泣いて、気づけば朝になっている。
生徒たちの名前を思い出しても、胸の奥が冷たくなる。
もう、誰かを導く光になんてなれない。
私が燃え尽きて、灰になってしまったから。
——それでも、明日も授業はある。
鏡の前で笑顔を作る練習をしながら、今日も
心のどこかで小さく呟く。
「もう少しだけ、壊れる音を我慢しよう」
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください

ななしさん
はじめまして。
二児の子を持つ母です。
もう子供達はある程度大きいです。
子供を育ててきた者として思うのは、
「叱っても褒めても届かない。」
そういうものだということです。
素直に聞いてくれたら儲け物。
むしろ素直すぎる子も心配だったりします。
どこかで我慢をしているかもしれないですからね。
でも決してむだではありません。
聞き流されたようでも、心のどこかに引っかかって、忘れられたようでも、本人ももしかしたら気づかないくらいでも、残っていたりするものです。
周りの大人たちが何度も話して聞かせることで、いつの間にかかたちになったりするものです。
あなたはそのうちの一回か、数回だったとしても、子供達のことを思いする発言ならば、決して無駄ではありません。
なるべくなら褒めるのを多くする方のがいいでしょう。
危険な時は気持ちが伝わるように叱り、
人に迷惑がかかることなら話して聞かせる。
学校で習ったりしているかもしれませんが、
赤ちゃんに注意をする時は、目を見て、声を低くして叱ります。声が高いと言葉のわからない赤ちゃんは怒られてるのが分からないんですって。
もう言葉は分かっている子供達でしょうけど、そのように雰囲気でも真剣さを伝える事は大事かもしれません。
「あなたには教師の資質がない。」
すごい事言いますね。
子供の事をイジメる、盗撮などの犯罪行為をするなどの余程の事がないと言えれないかなと。
そんな事はないのでしょう?
よく断言できますね。
そんな事もないのにそんな発言をするなんて、私はその人の社会人としての資質を疑いますよ。
私もPTAや子供会で役をした事もありますし、子供達を通していろんな親と関わってきました。
すごいと思えるような立派な親御さんもいれば、何この人?というような人もいます。
その時々により見せる姿が違う事もあるかもしれませんし…。
ちょっと驚くような残念な言動をする親御さんはけっこういます。
ショックだとは思いますがそういうものです。
難しいと思いますが、できるだけ流してしまうのがいいと思います。
同じ学校の先生とか、同じく先生をしている学校時代の友達とかに話を聞いてもらえたらいいのかなあ。とか思います。
たくさんのことを学び、実習もして、資格も取ってそこにいるはずです。
そこを越えれた時点で、ある程度資質はあるという事ではないでしょうか。
そんな人の言葉より、その事を信じて、自分が培ってきたものを信じて、立っていて下さい。

ななしさん
小説みたいですね。教科は国語の先生ですか。
 yuki.
yuki.
教師と言う職業は昔は尊敬されてたはずなんですがね…。
少なくとも90年代の平成初期に小学生だったときは小5の嫌いだった担任を除き尊敬してました。
小6に進級した時に担任の先生が児童から人気のあったすごく優しい先生に決まった時は歓喜の声があがったくらいに。
今の先生は大変だと思います。
ちょっと叱ったり注意すれば体罰だの虐待だの言葉の暴力だのハラスメントだのとクレーム。
多様性への配慮だのと呼び方1つとっても気にしないといけない。
まあ昔は昔で体育の時に水を飲んじゃいけないとか明らかにおかしい指導はありましたが…
今の教育現場ってよっぽどの聖人か、
よっぽど割り切った人じゃないとやってけないんじゃないかって思いますね。
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください