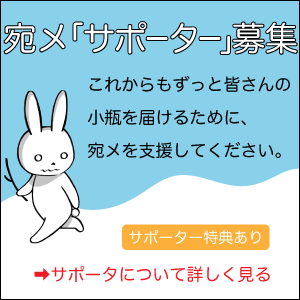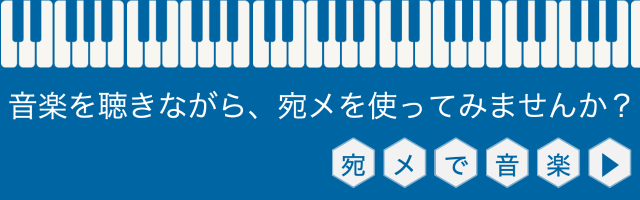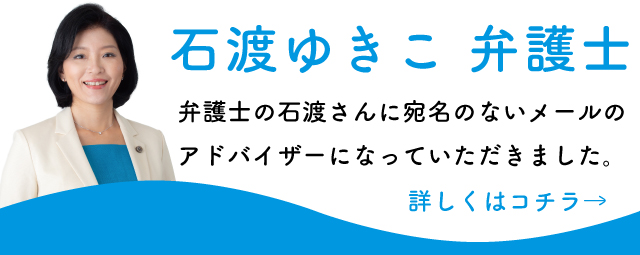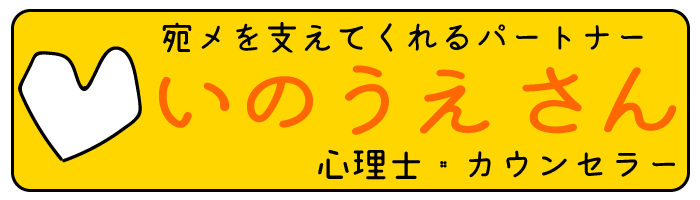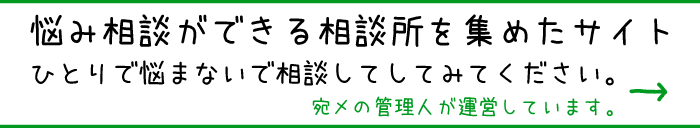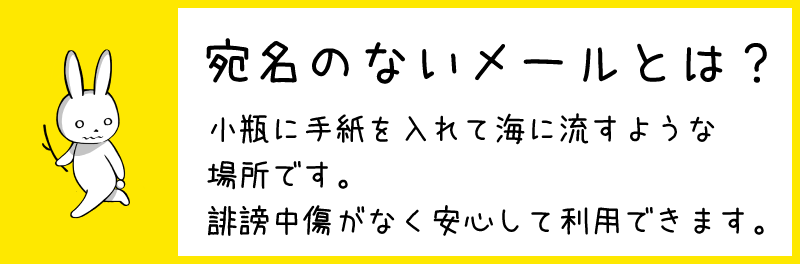
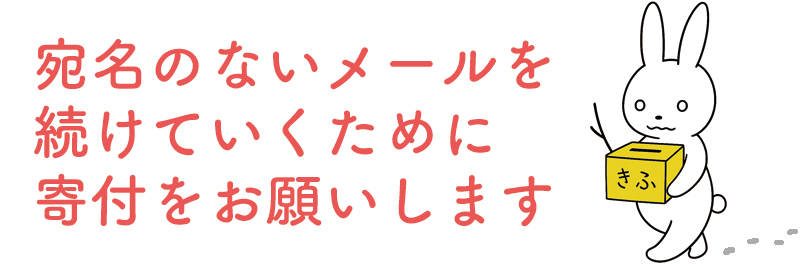
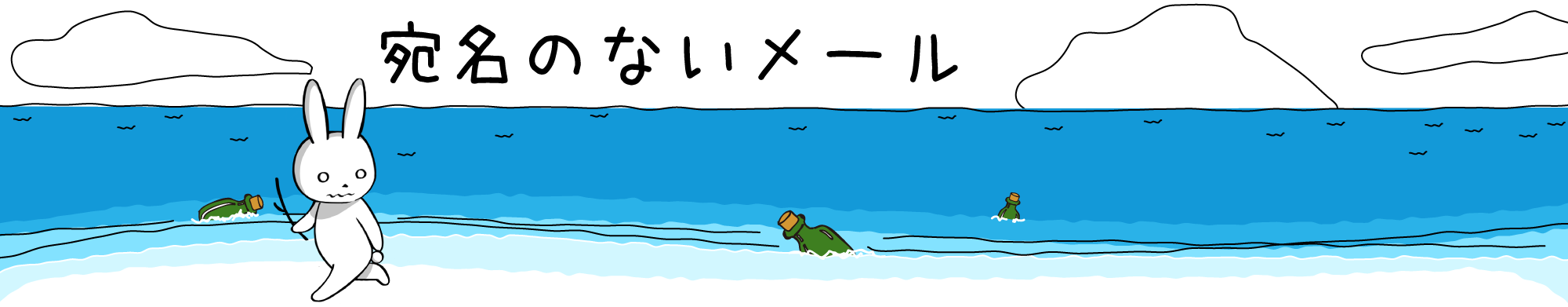
僕の現在位置です
興味深い内容の医学論文を読んだので、それについて少し記そうかなと。
頭痛の原因と食事習慣のこと。
といっても、よく話題に上るチョコレートや赤ワインの影響ではなくて、食事と密接に関係している“意外な感染症”の話——。
__________
アメリカ人、52歳男性。
片頭痛・2型糖尿病・肥満症の既往あり。
直近の4ヶ月間に片頭痛の増悪を認め、頓服治療に抵抗性を示している。
海外渡航歴は2年前のバハマへのクルーズ参加のみ。
食習慣として、生もの・屋台食を拒否する一方、軽く炙っただけの生ベーコンを長きにわたり喫食してきたことが特徴的である。
__________🖋
この患者さん、はじめに頭のCTを撮ったときに、左右両方の大脳皮質深部、脳室近くの白質実質にたくさんの嚢胞病巣が見つかっている。
入院前の精査で MRI をやったところ、T2 強調/FLAIR 像で高信号域(白く写る部分)を認め、読影の結果は「脳梁と後頭葉に大きな嚢胞病巣があって、その周りがむくんでいる」というもの。
初診を担当した脳外科医は、患者さんの言うベーコンの話と画像検査の結果から、何らかの感染症に罹っているのでは、と考えた(これすごい)。
術的介入はせず、感染症科にコンサルテーションを行った。
徹底的な感染症の検査(血清・尿)で嚢虫症 IgG シスト抗体が陽性だったので、神経嚢虫症が疑われた。
てんかん発作を防いで脳のむくみを取るためにステロイド薬を、脳に寄生した虫をやっつけるために駆虫薬2種をそれぞれ2週間投与したところ、病変が小さくなり頭痛も改善した。
——と、いきさつはこんな感じ。
神経嚢虫症は、動物の生肉に潜む Taenia solium(有鉤条虫)がヒトの中枢神経系に寄生することで起こる感染症。
開発途上国の風土病とも言われるけど先進国でも症例があって、今回の論文にもあった頭痛、そして世界的に報告が多いのはてんかん発作で、しばしば致死的な経過をたどることがあるんだ。
ここ日本で一番多いとされる発症原因は、ズバリ「加熱不足の豚肉を食べること」。スーパーの精肉売場に【召し上がる前に、中心まで十分に加熱してください】という札が付いてるのを見たことがある人も多いと思う。
キャンプブームの前にはジビエが流行ったし、家庭での低温調理も一般的になってきたけど、作るときには細心の注意を払って、ちょっとでも不安があったら“食べない”選択を考えてほしいな。
そう、肉にかかわる感染症のことでもう一つ。
2011年に起きた集団食中毒では、腸管出血性大腸菌に汚染された牛肉を食べた5人が亡くなっているけど、実は食中毒そのものが原因じゃなかった。
それらの大腸菌に感染したあとに合併することが多い病気として、HUS(溶血性尿毒症症候群)がよく知られている。
実際に5人は HUS で命を落としているし、このうち一人の少年は重い脳症をきたしたあとに脳死状態になっていた。
食中毒を起こしても、お腹の不調で済めばまだいい——この手の大腸菌は、消滅間際に悪いもの(Vero 毒素,VT)をばらまく、厄介なやつ。
こいつによく反応する細胞は腸・腎臓・脳に集中していて、VT は細胞膜を破った先の真核細胞にあるリボソームの構造を変化させる(アデニン離断)。
すると、日頃からリボソームを栄養してきた tRNA(エネルギーの運び屋)が結合できなくなるので、細胞全体がアミノ酸不足に陥る。
改変されたリボソームは、mRNA(転写された DNA の一部)の情報をもとにタンパク質を合成することができないまま飢餓状態になり、最後はアポトーシスへと導かれ細胞ごと消えてしまうんだ。
この細胞消滅が腸で起きれば大量出血するし、腎臓なら毛細血管や赤血球が壊されて溶血する、脳であれば急性脳症を引き起こす……それがこの感染症の恐ろしさ。
(ここらに興味ある人は理科の教員とか医師に訊くと情報もらえるかも)
精肉売場の各種お肉は、火を通して食べる前提で流通してる。
とくに牛のレバ刺し提供が禁止されたあと、代替品として豚のレバ刺しを口にする人が増えて、HEV(E型肝炎ウィルス)の感染報告が相次いだ時期もあったからご注意を。
ちなみに、加熱指示のないウィンナー・ソーセージはそのまま食べても心配いらないし、生のまま流通してるベーコンってほぼ見ないし(一部の輸入品や自家製のものは要確認かな)、製造工程で水分活性が厳しく管理されてる生ハムも大丈夫。
ビーフステーキをレアで食べるのも問題ないけど、心理的に抵抗ある人はいつも通りに焼いてからのほうが安心、かもね。
ちょっとぐらい中が赤くてもいいでしょ、と思ってしまいがちだけど……。
時として命に関わる事態にもなりかねないから、気に留めてみてほしいなぁ。
以上、「自分の体は自分で守ろう!」という提案でした🌟
♫地球蝕 / Q flavor
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください
 僕の現在位置@joqr.net
僕の現在位置@joqr.net
お返事ありがとうございます。
わさび醤油で漬けた生の鶏ササミ、レシピサイトでもたくさん出てきますね。
「銘柄鶏を選んで」「新鮮な肉を使えばOK」そんな言葉も並んでいます。
鶏肉といえば、季節問わずカンピロバクター属の細菌に気をつけたいです。
保菌者である鶏は無症状ですが、ヒトに感染すると3~7日の潜伏期間を経て、辛いつらい消化器症状がやってきます。
2021年報告(2020年度調査)の名古屋市保健所による肉汚染状況データでは、お店で飲食に供された生鶏・鶏タタキの原料の41%が、カンピロバクター陽性だったとのこと。
これを多いと見るかどうかは個人差あるので数字の提示に留めますが……。
僕らなんか見てて怖いな~と思うのは、銘柄鶏なら大丈夫という謎の安全神話はともかく、「鶏肉が新鮮であればあるほど、肉表面の生菌数が保たれる」これを知らないかたが多いことですね。
カンピロバクターって実は低温環境に強くて、4℃程度の冷蔵保存で6日ぐらい、-20℃の冷凍だと3ヶ月ぐらい生きられます。
冷蔵庫に入れて6日も生きてるとなれば、消費期限までしっかり菌がいるということなので、体を守るためにもやはり「加熱しましょう」というお話になろうかと思います。
鶏専門のお店で多いメニューといえば「鶏刺し」や「鶏ハツのお造り」でしょうか。
現行の食品衛生法には鶏肉に関する規定がないので、“鶏の生食”の定義も提供方法も、販売店や飲食店が自由に決めてよいことになっています。
もちろん、お店の責任で食中毒を起こせば営業停止などの行政処分は免れませんが、停止が解ければまた、そのお店は生鶏を出すかもしれません……制限がないので。
九州地方では、古くからの伝統として鶏の生食が当たり前になっていますよね。
宮崎・鹿児島の両県では「生食用食鳥の衛生管理基準」を定めていて、それに適合した肉だけが生食用として流通します。
ただ、生食用というのは生菌数を減らす努力をしている肉という意味であって、生で食べて食中毒を起こさないことを保証するものではないです。
乳幼児・高齢者・免疫が低下した方には、個人的には推奨しません(「食べない/食べさせない選択もできたよね」ということで、結局“自己責任”で終わってしまうのは哀しい)。
僕もブリ大根は好物で、夏の暑い日でも食べちゃいます。
ブリであればお刺身で食べられますので、生の鶏肉よりリスクはずっと低いと思われます。
昭和の頃ですと、素手で握ったおむすびに付いた黄色ブドウ球菌、生魚に付いた腸炎ビブリオ菌が蔓延っていましたが、今やカンピロバクターとノロウィルスが食中毒の原因のツートップ。
ノロは冬が多いですが、カンピロちゃんは通年で注意したいですね。
MAP包装は画期的な技術だと思いますし、鮮度保持、食品ロス低減に役立っていますが(フィルムがピンと張って見た目も綺麗)、菌を減らす効果は期待できないので、面倒でも加熱! です。
美味しく楽しい食生活をお送りください。

ななしさん
過去、何回か生食をしてしまった者です。
醤油わさびで漬け込んだ鶏のササミやブリ大根用のブリなど。漬けダレと合わせての生食は正直、禁忌の味です。たまたま無事でいられましたが気をつけたいと思います。
特にこれからの時期はすぐお肉は傷みやすくなりますしね。ついつい放置して肉が灰色や紫色になったこと数知れずです。
とはいえここ数年はMAP包装のおかげで助かっています。未開封のものなら以前より少し長保ちしますね。
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
▶ お返事の注意事項